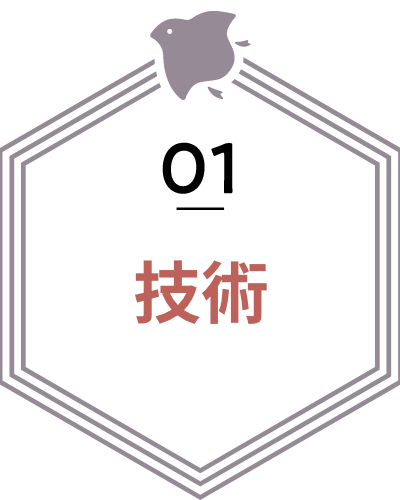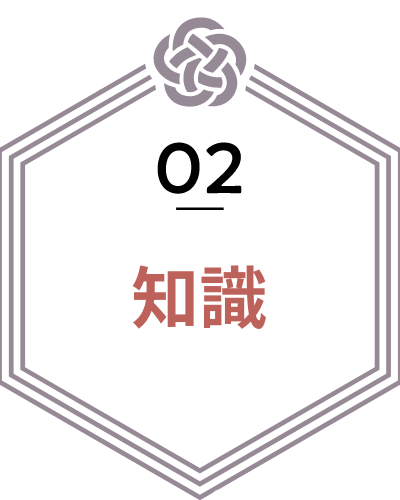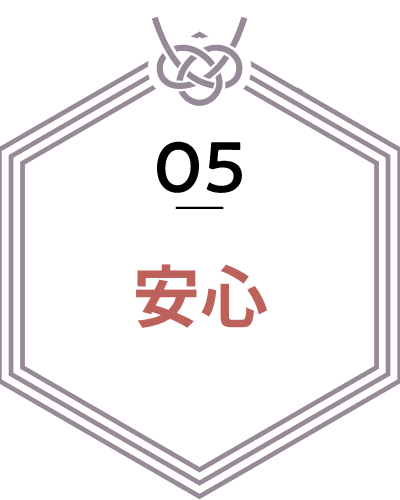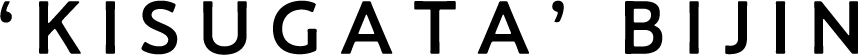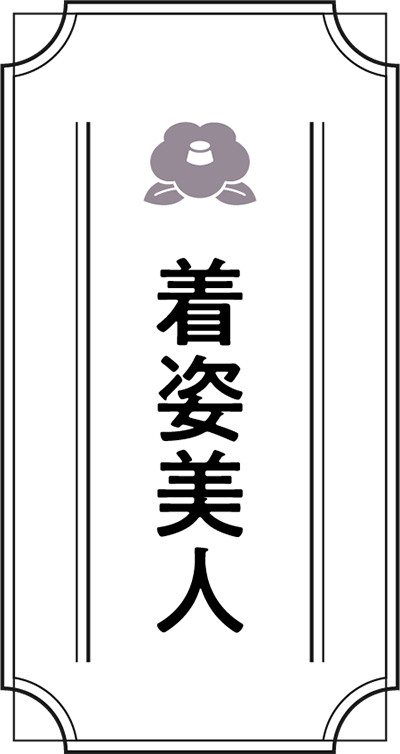① ゆったり綺麗に着られる「技術」
② 着て出掛ける、⾃信を持って楽しむ為の「知識」
③ 魅力的なモノ作りの職人とお客様を直接つなぐ「産直商品」
④ きものを着て楽しむ体験「着る機会」
⑤ 着た後の安⼼(クリーニング、アフターサービス等)
「きものを着て楽しむ方にとって
大切な要素を総合的にご提供」
-
着て楽しむ為の知識きものカレッジ
季節やお出掛けする場面に合わせたコーディネート、合わせ方や活用方法、保存や手入れなど、ご自身で楽しむ為の知識を、教室やカレッジなどでメーカー(生産者)が直接お教えしています。
-
着て出掛けたくなる産直きもの
咲久紗では老舗メーカーと直接繋がり、産地直送のきものや帯を提供しています。教室やカレッジで生産者から直に学びながら、こだわりの品質を試したり、お手ごろな価格で手に入れることができます。